穴埋め式4択クイズ (50問)
- 将棋の「棋士」とは、本将棋を______とする人のことを指す。
- A) 趣味
- B) 職業
- C) 研究
- D) 遊び
- 正解: B) 職業
- 説明: 将棋の「棋士」は、本将棋を職業(専業)とする人を意味し、現代では日本将棋連盟に所属する四段以上の者を指します。
- 現代の将棋棋士は、日本将棋連盟に所属する______以上の段位を持つ者である。
- A) 二段
- B) 三段
- C) 四段
- D) 五段
- 正解: C) 四段
- 説明: 日本将棋連盟では、四段以上の段位を持つ者がプロ棋士として認められます。
- 棋士とは別に、女性向けのプロ制度として存在するのは______である。
- A) 指導棋士
- B) 女流棋士
- C) アマチュア棋士
- D) 若手棋士
- 正解: B) 女流棋士
- 説明: 将棋には棋士(男女問わず)と女流棋士(女性限定)の2つのプロ制度が併存しています。
- 日本将棋連盟はアマチュアの将棋愛好者を「棋士」ではなく______と呼ぶ。
- A) 選手
- B) 愛好家
- C) 指し手
- D) 観客
- 正解: A) 選手
- 説明: アマチュア大会に出場する者は「アマチュア棋士」ではなく「選手」と呼ばれます。
- 囲碁のプロも「棋士」と呼ばれるため、将棋の棋士は区別のために______と呼ばれることがある。
- A) 本将棋棋士
- B) 将棋棋士
- C) プロ棋士
- D) 日本棋士
- 正解: B) 将棋棋士
- 説明: 囲碁と将棋のプロが共に「棋士」と呼ばれるため、「将棋棋士」と表現されることがあります。
- 江戸時代以前、将棋を指す者は一般に______と呼ばれていた。
- A) 将棋指し
- B) 棋士
- C) 専門棋士
- D) 棋客
- 正解: A) 将棋指し
- 説明: 江戸時代以前は、プロアマ問わず「将棋指し」と呼ばれていました。
- 将棋連盟の結成と新聞棋戦賞金の収入によって確立した呼称は______である。
- A) 棋士
- B) 専門棋士
- C) 将棋指し
- D) プロ棋士
- 正解: B) 専門棋士
- 説明: 将棋連盟の成立と共に「専門棋士」という呼称が広まりました。
- 昭和初期、専門棋士の社会的地位は低く、地方では______のように見られていた。
- A) 学者
- B) 芸術家
- C) バクチ打ち
- D) 商人
- 正解: C) バクチ打ち
- 説明: 当時、専門棋士は賭博に関連するイメージから「バクチ打ち」と見られることがありました。
- 「棋士」と自称するのが一般的になったのは______以降とされる。
- A) 江戸時代
- B) 明治時代
- C) 大正時代
- D) 戦後
- 正解: D) 戦後
- 説明: 大山康晴や戦後のプロから「棋士」という自称が一般的になりました。
- 昭和9年頃、プロ棋士になる基準は______からだったが、現在は四段からである。
- A) 初段
- B) 二段
- C) 三段
- D) 四段
- 正解: A) 初段
- 説明: 昭和9年頃は初段から専門棋士とされましたが、奨励会の制度確立で四段からに変更されました。
- 棋士の主な収入源は、棋戦での______である。
- A) 指導料
- B) 対局料と賞金
- C) 印税
- D) イベント出演料
- 正解: B) 対局料と賞金
- 説明: 棋士の収入は主に棋戦参加による対局料と賞金で成り立っています。
- 棋士が将棋教室を経営して得る収入は、対局料以外の______の一つである。
- A) 主収入
- B) 副収入
- C) 臨時収入
- D) 賞金
- 正解: B) 副収入
- 説明: 将棋教室経営や著書の印税などは副収入として挙げられています。
- 出張指導や詰将棋作成の謝礼には、日本将棋連盟が定めた______がある。
- A) 料金表
- B) 契約書
- C) 賞金基準
- D) 指導マニュアル
- 正解: A) 料金表
- 説明: 出張指導などの謝礼は連盟の規定料金表に基づきます。
- 昭和30年代頃、多くの棋士が______の嘱託社員として収入を得ていた。
- A) 出版社
- B) 新聞社
- C) テレビ局
- D) 学校
- 正解: B) 新聞社
- 説明: 升田幸三や大山康晴らは新聞社の嘱託社員として記事執筆で収入を得ていました。
- 2020年頃から、棋士の中には______活動で収入を得る者もいる。
- A) YouTuber
- B) 教師
- C) ライター
- D) 画家
- 正解: A) YouTuber
- 説明: 一部の棋士はYouTubeチャンネルを開設し、活動しています。
- 日本将棋連盟では、棋士に______を付与している。
- A) 称号
- B) 棋士番号
- C) 段位証明書
- D) 賞金ランク
- 正解: B) 棋士番号
- 説明: 棋士(引退者含む)には棋士番号が付与されます。
- 2010年に女流棋士の清水市代が敗れた相手は、コンピュータ将棋の______である。
- A) ボンクラーズ
- B) あから2010
- C) dlshogi
- D) 将棋電王
- 正解: B) あから2010
- 説明: 清水市代は2010年に「あから2010」に敗れました。
- 2012年、引退後の米長邦雄がコンピュータ将棋______に敗れた。
- A) ボンクラーズ
- B) あから2010
- C) dlshogi
- D) 将棋電王
- 正解: A) ボンクラーズ
- 説明: 米長邦雄は2012年の将棋電王戦でボンクラーズに敗れました。
- 奨励会ができたのは、東京では昭和______年である。
- A) 3年
- B) 9年
- C) 10年
- D) 61年
- 正解: A) 3年
- 説明: 東京の奨励会は昭和3年(1928年)に設立されました。
- 大阪の奨励会が設立されたのは昭和______年である。
- A) 3年
- B) 9年
- C) 10年
- D) 61年
- 正解: C) 10年
- 説明: 大阪の奨励会は昭和10年(1935年)に設立されました。
- 1986年、______九段が将棋界7人目の褒章受章者となった。
- A) 大山康晴
- B) 升田幸三
- C) 広津久雄
- D) 中原誠
- 正解: C) 広津久雄
- 説明: 広津久雄九段は1986年に藍綬褒章を受章しました。
- 棋士のプロ制度が確立したのは______の結成がきっかけである。
- A) 日本将棋連盟
- B) 奨励会
- C) 新聞社連合
- D) 将棋協会
- 正解: A) 日本将棋連盟
- 説明: 日本将棋連盟の結成と新聞棋戦がプロ制度の基盤となりました。
- 大山康晴が少年時代にプロを指した呼称は______である。
- A) 将棋指し
- B) 棋士
- C) 専門棋士
- D) 棋客
- 正解: C) 専門棋士
- 説明: 大山康晴によると、昭和初期には「専門棋士」と呼ばれていました。
- 棋士が「棋士」と呼ばれるようになったのは______の影響が大きい。
- A) 大山康晴
- B) 升田幸三
- C) 中原誠
- D) 藤井聡太
- 正解: A) 大山康晴
- 説明: 大山康晴や戦後のプロから「棋士」という呼称が一般的になりました。
- コンピュータ将棋がプロを超えたのは______年代である。
- A) 1990年代
- B) 2000年代
- C) 2010年代
- D) 2020年代
- 正解: C) 2010年代
- 説明: 2010年代にコンピュータ将棋がプロを超える能力を持つようになりました。
- 棋士の収入源として、______に関する著書の印税がある。
- A) 小説
- B) 将棋
- C) 歴史
- D) 料理
- 正解: B) 将棋
- 説明: 将棋に関する著書の印税は棋士の収入源の一つです。
- 棋士がイベント出演で得る報酬は______と呼ばれる。
- A) 謝礼
- B) 賞金
- C) 対局料
- D) 指導料
- 正解: A) 謝礼
- 説明: イベント出演や詰将棋作成に対する報酬は「謝礼」と呼ばれます。
- 棋士の段位は______から九段までである。
- A) 初段
- B) 二段
- C) 三段
- D) 四段
- 正解: D) 四段
- 説明: プロ棋士の段位は四段から九段までで、三段以下は奨励会です。
- 奨励会の段級位と棋士の段位は______している。
- A) 独立
- B) 連続
- C) 分離
- D) 重複
- 正解: B) 連続
- 説明: 奨励会の三段から四段に昇段することでプロ棋士となります。
- 棋士の______は、日本将棋連盟の正式名称である。
- A) 称号
- B) 棋士
- C) 段位
- D) 番号
- 正解: B) 棋士
- 説明: 現在、「棋士」は日本将棋連盟のプロの正式名称です。
- 将棋のプロが「棋士」と呼ばれるようになったのは______時代以降である。
- A) 明治
- B) 大正
- C) 昭和
- D) 平成
- 正解: C) 昭和
- 説明: 大山康晴や戦後のプロから「棋士」が一般的になりました。
- 棋士の社会的地位が低かったのは______時代である。
- A) 江戸
- B) 明治
- C) 大正
- D) 昭和初期
- 正解: D) 昭和初期
- 説明: 昭和初期には専門棋士がバクチ打ちのように見られていました。
- 奨励会の設立により、プロ棋士の基準が______に変更された。
- A) 初段
- B) 二段
- C) 三段
- D) 四段
- 正解: D) 四段
- 説明: 奨励会の設立で「四段からプロ棋士」という制度が確立しました。
- 棋士の収入源として、______の対局料が主軸である。
- A) イベント
- B) 棋戦
- C) 指導
- D) 教室
- 正解: B) 棋戦
- 説明: 棋戦での対局料と賞金が主な収入源です。
- 棋士がYouTuberとして活動し始めたのは______頃からである。
- A) 2010年
- B) 2015年
- C) 2020年
- D) 2025年
- 正解: C) 2020年
- 説明: 2020年頃から棋士がYouTube活動を始めています。
- 棋士番号は______にも付与される。
- A) 現役棋士
- B) 引退棋士
- C) 女流棋士
- D) 指導棋士
- 正解: B) 引退棋士
- 説明: 棋士番号は引退棋士を含む全ての棋士に付与されます。
- コンピュータ将棋「あから2010」に敗れたのは______である。
- A) 大山康晴
- B) 升田幸三
- C) 清水市代
- D) 中原誠
- 正解: C) 清水市代
- 説明: 2010年に清水市代が「あから2010」に敗れました。
- 将棋電王戦で米長邦雄が敗れた相手は______である。
- A) ボンクラーズ
- B) あから2010
- C) dlshogi
- D) 将棋電王
- 正解: A) ボンクラーズ
- 説明: 2012年の将棋電王戦で米長邦雄がボンクラーズに敗れました。
- 奨励会の設立は______がきっかけでプロ制度が確立した。
- A) 新聞棋戦
- B) 日本将棋連盟
- C) 大山康晴
- D) コンピュータ将棋
- 正解: B) 日本将棋連盟
- 説明: 日本将棋連盟と奨励会の設立がプロ制度の基盤となりました。
- 棋士の副収入として、______の経営がある。
- A) 将棋教室
- B) レストラン
- C) 書店
- D) 工場
- 正解: A) 将棋教室
- 説明: 将棋教室の経営は棋士の副収入源の一つです。
- 棋士が詰将棋作成で得る謝礼は______に基づく。
- A) 契約書
- B) 料金表
- C) 賞金基準
- D) 指導料
- 正解: B) 料金表
- 説明: 詰将棋作成の謝礼は連盟の料金表に基づきます。
- 昭和30年代、棋士が新聞社の______として収入を得ていた。
- A) 記者
- B) 編集者
- C) 嘱託社員
- D) 経営者
- 正解: C) 嘱託社員
- 説明: 多くの棋士が新聞社の嘱託社員として記事を書いていました。
- 棋士がYouTubeで活動するようになったのは______の影響もある。
- A) コンピュータ将棋
- B) 2020年
- C) 新聞棋戦
- D) 奨励会
- 正解: B) 2020年
- 説明: 2020年頃からYouTuber活動が始まりました。
- 棋士に付与される______は引退後も保持される。
- A) 称号
- B) 棋士番号
- C) 段位
- D) 賞金
- 正解: B) 棋士番号
- 説明: 棋士番号は引退棋士にも付与されたままです。
- コンピュータ将棋がプロを超えたのは______の出来事が象徴的である。
- A) 清水市代の敗北
- B) 米長邦雄の敗北
- C) 大山康晴の敗北
- D) 升田幸三の敗北
- 正解: A) 清水市代の敗北
- 説明: 2010年の清水市代の敗北がプロ超えの象徴です。
- 棋士の収入源として、______に関するイベント出演がある。
- A) 将棋
- B) 囲碁
- C) チェス
- D) 麻雀
- 正解: A) 将棋
- 説明: 将棋関連のイベント出演が収入源の一つです。
- 棋士の______は日本将棋連盟によって管理されている。
- A) 賞金
- B) 棋士番号
- C) 指導料
- D) 印税
- 正解: B) 棋士番号
- 説明: 棋士番号は連盟が付与・管理しています。
- 2010年代、コンピュータ将棋がプロを超えたのは______の登場による。
- A) あから2010
- B) ボンクラーズ
- C) dlshogi
- D) 将棋電王
- 正解: A) あから2010
- 説明: 「あから2010」が清水市代に勝利し、プロ超えが注目されました。
- 棋士のプロ制度が現在の形になったのは______の影響である。
- A) 奨励会
- B) 新聞棋戦
- C) 日本将棋連盟
- D) コンピュータ将棋
- 正解: C) 日本将棋連盟
- 説明: 日本将棋連盟の設立が現在のプロ制度の基盤です。
- 棋士が「専門棋士」と呼ばれたのは______時代である。
- A) 江戸
- B) 明治
- C) 大正
- D) 昭和初期
- 正解: D) 昭和初期
- 説明: 大山康晴によると、昭和初期に「専門棋士」と呼ばれていました。
選択式4択クイズ (50問)
- 将棋の「棋士」とはどのような人を指すか?
- A) 将棋を趣味とする人
- B) 本将棋を職業とする人
- C) 将棋の研究者
- D) 将棋の指導者
- 正解: B) 本将棋を職業とする人
- 説明: 棋士は本将棋を職業とするプロを指します。
- 現代の棋士は何段以上の者か?
- A) 二段
- B) 三段
- C) 四段
- D) 五段
- 正解: C) 四段
- 説明: 日本将棋連盟では四段以上が棋士とされます。
- 棋士とは別に存在する女性向けのプロ制度は何か?
- A) 指導棋士
- B) 女流棋士
- C) アマチュア棋士
- D) 若手棋士
- 正解: B) 女流棋士
- 説明: 女流棋士は女性限定のプロ制度です。
- 日本将棋連盟がアマチュアを何と呼ぶか?
- A) 選手
- B) 愛好家
- C) 指し手
- D) 観客
- 正解: A) 選手
- 説明: アマチュアは「選手」と呼ばれます。
- 将棋棋士を囲碁棋士と区別する呼び方は何か?
- A) 本将棋棋士
- B) 将棋棋士
- C) プロ棋士
- D) 日本棋士
- 正解: B) 将棋棋士
- 説明: 「将棋棋士」と呼ばれます。
- 江戸時代以前に将棋を指す者を何と呼んだか?
- A) 将棋指し
- B) 棋士
- C) 専門棋士
- D) 棋客
- 正解: A) 将棋指し
- 説明: 「将棋指し」が一般的でした。
- 将棋連盟の結成で広まった呼称は何か?
- A) 棋士
- B) 専門棋士
- C) 将棋指し
- D) プロ棋士
- 正解: B) 専門棋士
- 説明: 「専門棋士」が広まりました。
- 昭和初期に棋士がどう見られていたか?
- A) 学者
- B) 芸術家
- C) バクチ打ち
- D) 商人
- 正解: C) バクチ打ち
- 説明: バクチ打ちのイメージがありました。
- 「棋士」という呼称が一般的になったのはいつからか?
- A) 江戸時代
- B) 明治時代
- C) 大正時代
- D) 戦後
- 正解: D) 戦後
- 説明: 戦後から一般的になりました。
- 昭和9年頃のプロ棋士の基準は何段だったか?
- A) 初段
- B) 二段
- C) 三段
- D) 四段
- 正解: A) 初段
- 説明: 初段から専門棋士とされていました。
- 棋士の主な収入源は何か?
- A) 指導料
- B) 対局料と賞金
- C) 印税
- D) イベント出演料
- 正解: B) 対局料と賞金
- 説明: 対局料と賞金が主です。
- 棋士の副収入に含まれるものは何か?
- A) 将棋教室の経営
- B) 主収入
- C) 臨時収入
- D) 賞金
- 正解: A) 将棋教室の経営
- 説明: 将棋教室経営は副収入です。
- 出張指導の謝礼に何が定められているか?
- A) 料金表
- B) 契約書
- C) 賞金基準
- D) 指導マニュアル
- 正解: A) 料金表
- 説明: 連盟の料金表が基準です。
- 昭和30年代に棋士が収入を得ていた職業は何か?
- A) 出版社
- B) 新聞社の嘱託社員
- C) テレビ局
- D) 学校
- 正解: B) 新聞社の嘱託社員
- 説明: 新聞社の嘱託社員として働いていました。
- 2020年頃から棋士が始めた活動は何か?
- A) YouTuber
- B) 教師
- C) ライター
- D) 画家
- 正解: A) YouTuber
- 説明: YouTuber活動が始まりました。
- 日本将棋連盟が棋士に付与するものは何か?
- A) 称号
- B) 棋士番号
- C) 段位証明書
- D) 賞金ランク
- 正解: B) 棋士番号
- 説明: 棋士番号が付与されます。
- 2010年に清水市代が敗れた相手は何か?
- A) ボンクラーズ
- B) あから2010
- C) dlshogi
- D) 将棋電王
- 正解: B) あから2010
- 説明: 「あから2010」に敗れました。
- 2012年に米長邦雄が敗れた相手は何か?
- A) ボンクラーズ
- B) あから2010
- C) dlshogi
- D) 将棋電王
- 正解: A) ボンクラーズ
- 説明: ボンクラーズに敗れました。
- 東京の奨励会が設立されたのはいつか?
- A) 昭和3年
- B) 昭和9年
- C) 昭和10年
- D) 昭和61年
- 正解: A) 昭和3年
- 説明: 昭和3年(1928年)に設立されました。
- 大阪の奨励会が設立されたのはいつか?
- A) 昭和3年
- B) 昭和9年
- C) 昭和10年
- D) 昭和61年
- 正解: C) 昭和10年
- 説明: 昭和10年(1935年)に設立されました。
- 1986年に褒章を受章した棋士は誰か?
- A) 大山康晴
- B) 升田幸三
- C) 広津久雄
- D) 中原誠
- 正解: C) 広津久雄
- 説明: 広津久雄が受章しました。
- 棋士のプロ制度を確立したのは何の結成か?
- A) 日本将棋連盟
- B) 奨励会
- C) 新聞社連合
- D) 将棋協会
- 正解: A) 日本将棋連盟
- 説明: 日本将棋連盟の結成がきっかけです。
- 大山康晴が少年時代に使った呼称は何か?
- A) 将棋指し
- B) 棋士
- C) 専門棋士
- D) 棋客
- 正解: C) 専門棋士
- 説明: 「専門棋士」と呼ばれていました。
- 「棋士」という呼称を一般化した棋士は誰か?
- A) 大山康晴
- B) 升田幸三
- C) 中原誠
- D) 藤井聡太
- 正解: A) 大山康晴
- 説明: 大山康晴の影響が大きいです。
- コンピュータ将棋がプロを超えたのはいつ頃か?
- A) 1990年代
- B) 2000年代
- C) 2010年代
- D) 2020年代
- 正解: C) 2010年代
- 説明: 2010年代に超えました。
- 棋士の収入源に含まれる著書のテーマは何か?
- A) 小説
- B) 将棋
- C) 歴史
- D) 料理
- 正解: B) 将棋
- 説明: 将棋に関する著書です。
- イベント出演で得る報酬の名称は何か?
- A) 謝礼
- B) 賞金
- C) 対局料
- D) 指導料
- 正解: A) 謝礼
- 説明: 「謝礼」と呼ばれます。
- 棋士の段位の最低は何段か?
- A) 初段
- B) 二段
- C) 三段
- D) 四段
- 正解: D) 四段
- 説明: 四段が最低です。
- 奨励会の段級位と棋士の段位の関係は何か?
- A) 独立
- B) 連続
- C) 分離
- D) 重複
- 正解: B) 連続
- 説明: 連続しています。
- 棋士の正式名称を管理するのはどこか?
- A) 日本将棋連盟
- B) 奨励会
- C) 新聞社
- D) 将棋協会
- 正解: A) 日本将棋連盟
- 説明: 日本将棋連盟が管理します。
- 「棋士」が一般的になった時代は何か?
- A) 明治
- B) 大正
- C) 昭和
- D) 平成
- 正解: C) 昭和
- 説明: 昭和時代以降です。
- 棋士の社会的地位が低かった時代は何か?
- A) 江戸
- B) 明治
- C) 大正
- D) 昭和初期
- 正解: D) 昭和初期
- 説明: 昭和初期に低かったです。
- プロ棋士の基準が四段になったのは何がきっかけか?
- A) 奨励会
- B) 新聞棋戦
- C) 日本将棋連盟
- D) コンピュータ将棋
- 正解: A) 奨励会
- 説明: 奨励会の設立がきっかけです。
- 棋士の収入の主軸は何か?
- A) イベント
- B) 棋戦
- C) 指導
- D) 教室
- 正解: B) 棋戦
- 説明: 棋戦が主軸です。
- 棋士がYouTuber活動を始めたのはいつ頃か?
- A) 2010年
- B) 2015年
- C) 2020年
- D) 2025年
- 正解: C) 2020年
- 説明: 2020年頃からです。
- 棋士番号が付与される対象は誰か?
- A) 現役棋士のみ
- B) 引退棋士を含む
- C) 女流棋士
- D) 指導棋士
- 正解: B) 引退棋士を含む
- 説明: 引退棋士にも付与されます。
- 「あから2010」に敗れた棋士は誰か?
- A) 大山康晴
- B) 升田幸三
- C) 清水市代
- D) 中原誠
- 正解: C) 清水市代
- 説明: 清水市代が敗れました。
- ボンクラーズに敗れた棋士は誰か?
- A) 大山康晴
- B) 米長邦雄
- C) 清水市代
- D) 中原誠
- 正解: B) 米長邦雄
- 説明: 米長邦雄が敗れました。
- 奨励会の設立がプロ制度に影響を与えたのはどこか?
- A) 東京
- B) 大阪
- C) 両方
- D) 京都
- 正解: C) 両方
- 説明: 東京(昭和3年)と大阪(昭和10年)の設立が影響しました。
- 棋士の副収入源として挙げられるものは何か?
- A) 将棋教室
- B) レストラン
- C) 書店
- D) 工場
- 正解: A) 将棋教室
- 説明: 将棋教室が副収入源です。
- 詰将棋作成の謝礼の基準は何か?
- A) 契約書
- B) 料金表
- C) 賞金基準
- D) 指導料
- 正解: B) 料金表
- 説明: 料金表が基準です。
- 昭和30年代に棋士が働いていたのはどこか?
- A) 出版社
- B) 新聞社
- C) テレビ局
- D) 学校
- 正解: B) 新聞社
- 説明: 新聞社の嘱託社員として働いていました。
- YouTuber活動が棋士に広まったのはいつか?
- A) 2010年
- B) 2015年
- C) 2020年
- D) 2025年
- 正解: C) 2020年
- 説明: 2020年頃からです。
- 棋士番号が保持されるのは誰か?
- A) 現役棋士
- B) 引退棋士
- C) 女流棋士
- D) 指導棋士
- 正解: B) 引退棋士
- 説明: 引退棋士も保持します。
- コンピュータ将棋のプロ超えを象徴する出来事は何か?
- A) 清水市代の敗北
- B) 米長邦雄の敗北
- C) 大山康晴の敗北
- D) 升田幸三の敗北
- 正解: A) 清水市代の敗北
- 説明: 2010年の清水市代の敗北が象徴的です。
- 棋士の収入源に含まれるイベントのテーマは何か?
- A) 将棋
- B) 囲碁
- C) チェス
- D) 麻雀
- 正解: A) 将棋
- 説明: 将棋関連イベントです。
- 棋士番号を管理するのはどこか?
- A) 日本将棋連盟
- B) 奨励会
- C) 新聞社
- D) 将棋協会
- 正解: A) 日本将棋連盟
- 説明: 日本将棋連盟が管理します。
- コンピュータ将棋がプロを超えたきっかけは何か?
- A) あから2010
- B) ボンクラーズ
- C) dlshogi
- D) 将棋電王
- 正解: A) あから2010
- 説明: 「あから2010」の勝利がきっかけです。
- 現在の棋士制度を確立したのは何か?
- A) 奨励会
- B) 新聞棋戦
- C) 日本将棋連盟
- D) コンピュータ将棋
- 正解: C) 日本将棋連盟
- 説明: 日本将棋連盟が確立しました。
- 「専門棋士」と呼ばれたのはどの時代か? – A) 江戸 – B) 明治 – C) 大正 – D) 昭和初期 – 正解: D) 昭和初期 – 説明: 昭和初期に呼ばれていました。
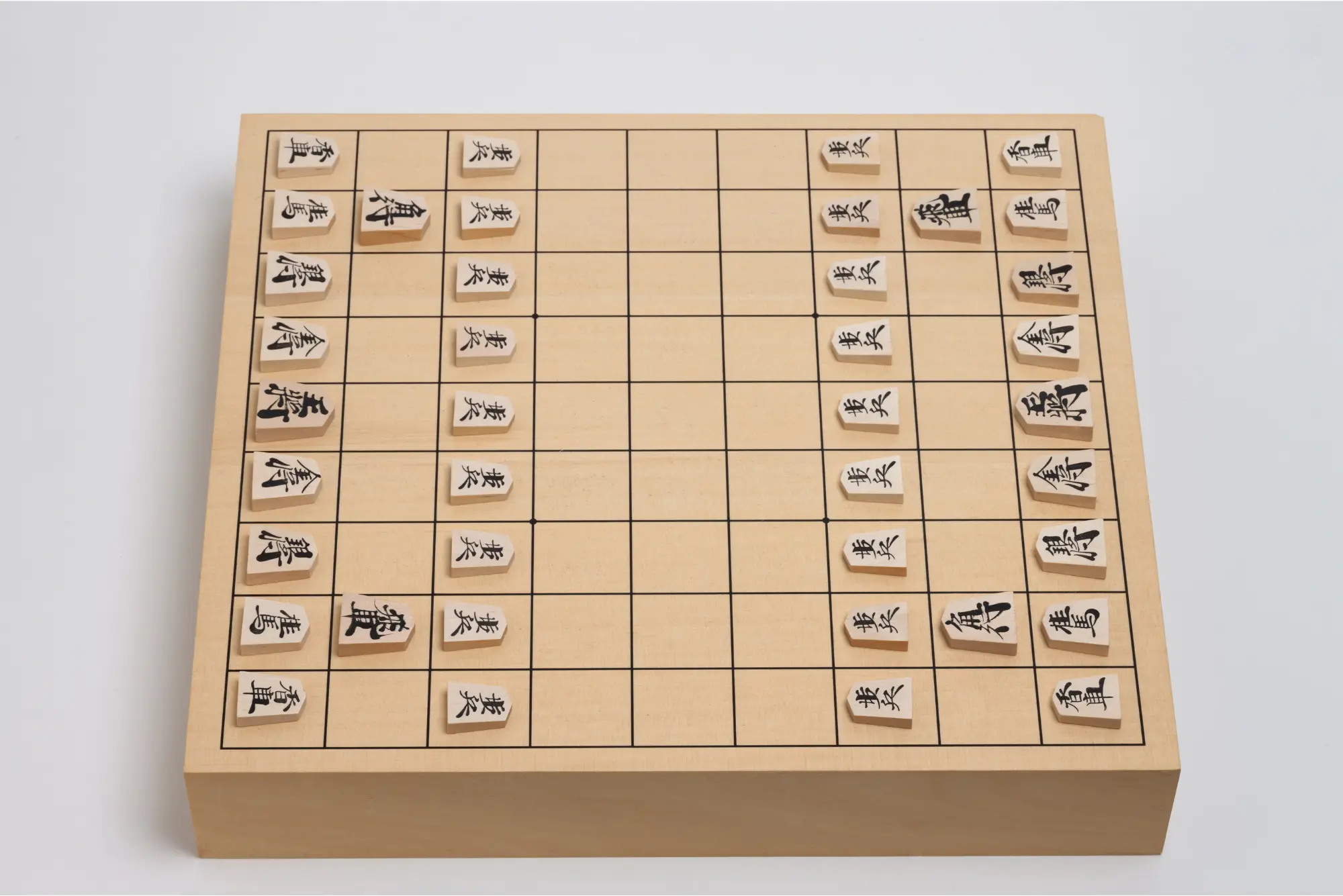








コメント