クイズの構成について
- 穴埋め式4択:文中の空欄に適切な用語を入れる形式。選択肢から正しいものを選ぶ。
- 選択式4択:質問に対して正しい答えを4つの選択肢から選ぶ形式。
- 答えの説明:各問題の正解を解説し、関連する将棋の知識や背景を補足。
1. 穴埋め式4択
問題1:双方が同じような陣形になる戦型や局面の状態を表す接頭辞を( )という。
a) 合駒 b) 相 c) 急戦 d) 持久戦
正解:b) 相
説明:将棋では、双方が同じような戦型や陣形を取る場合に「相」という接頭辞が使われます。例として「相居飛車」「相振り飛車」「相穴熊」などがあります。この用語は盤上の状況だけでなく、俗に盤外の事柄にも使われることがあります。
問題2:走り駒で王手されたとき、玉将を逃げずに相手の駒の利きに駒を打ったり動かしたりして王手を解除することを( )という。
a) 合駒 b) 詰み c) 入玉 d) 千日手
正解:a) 合駒
説明:合駒とは、相手の走り駒(飛車、角行、香車など)の利きを遮るために、自分の駒を打ったり動かしたりして王手を防ぐことです。「間遮(あいしゃ)」とも呼ばれ、実戦でよく使われる重要な技術です。
問題3:序盤に一方が突いた端歩に応じてもう一方も同じ筋の歩を突くことを( )という。
a) 合駒請求 b) 相端歩 c) 手待ち d) 急戦
正解:b) 相端歩
説明:相端歩とは、序盤で一方が端歩(1筋または9筋の歩)を突いた際に、相手も同じ筋の歩を突く手筋を指します。これは手筋の一つであり、必ずしも行う必要はありませんが、バランスを取るために有効な手段です。
2. 選択式4択
問題4:次のうち、将棋で「走り駒」と呼ばれる駒はどれですか?
a) 金将 b) 銀将 c) 飛車 d) 桂馬
正解:c) 飛車
説明:走り駒とは、1マス以上遠くまで移動できる長距離の利きを持つ駒のことで、具体的には飛車、角行、香車(およびそれらの成駒である竜王、竜馬)を指します。金将や銀将、桂馬は近距離の駒であり、走り駒には含まれません。
問題5:次のうち、対局者がお互いに穴熊戦法を採用した戦型を何と呼びますか?
a) 相居飛車 b) 相穴熊 c) 相振り飛車 d) 相矢倉
正解:b) 相穴熊
説明:相穴熊とは、両対局者がともに穴熊戦法(玉を端に寄せ、堅固に囲う戦法)を採用した戦型のことです。持久戦になりやすく、プロの対局でもよく見られる形です。
問題6:次のうち、玉将を敵陣に入れることを何と呼びますか?
a) 詰み b) 入玉 c) 千日手 d) 合駒
正解:b) 入玉
正解:入玉とは、玉将を敵陣(相手の3段目以内)に進出させることです。入玉すると玉が詰みにくくなり、持将棋(引き分け)や逆転の可能性が高まります。特に長時間の対局で重要な戦略です。
3. 穴埋め式4択
問題7:対局者が同じ手順を繰り返し、局面が進展しない状態を( )という。
a) 詰み b) 千日手 c) 入玉 d) 合駒
正解:b) 千日手
説明:千日手とは、両対局者が同じ手順を繰り返し、局面が全く進展しない状態を指します。ルール上、4回同じ局面が繰り返されると引き分けとなります。実戦では、千日手を避けるために新たな手を考える必要があります。
問題8:玉将が敵陣に入り、双方が入玉した状態を( )という。
a) 相入玉 b) 相居飛車 c) 相振り飛車 d) 相穴熊
正解:a) 相入玉
説明:相入玉とは、双方の玉将が敵陣に入った状態を指します。この場合、どちらも詰みにくくなるため、持将棋(引き分け)になる可能性が高まります。プロの対局では、入玉を巡る駆け引きが重要です。
問題9:相手の駒を取らずに、自分の駒を相手の駒の利きに進めることを( )という。
a) 合駒 b) 浮き駒 c) 捨て駒 d) 飾り駒
正解:c) 捨て駒
説明:捨て駒とは、自分の駒を相手の駒の利きに進めることで、相手に取らせることを前提とした手筋です。取らせた後に反撃や攻めの形を作るために使われます。戦略的な局面でよく見られる技術です。
4. 選択式4択
問題10:次のうち、将棋で「大駒」と呼ばれる駒はどれですか?
a) 歩兵 b) 桂馬 c) 飛車 d) 銀将
正解:c) 飛車
説明:大駒とは、将棋において価値が高く、遠距離の利きを持つ駒のことで、具体的には飛車と角行を指します。対して、歩兵、桂馬、銀将などは「小駒」と呼ばれます。大駒は攻守の要となる重要な駒です。
問題11:次のうち、対局後に棋譜を見ながら振り返りを行うことを何と呼びますか?
a) 感想戦 b) 公開対局 c) 封じ手 d) 振り駒
正解:a) 感想戦
説明:感想戦とは、対局終了後に両対局者が棋譜を見ながら、試合の進行や手順について振り返り、意見を交換することを指します。プロの対局では、感想戦を通じて学びや反省が行われます。
問題12:次のうち、相手の玉を確実に詰ませる状態を何と呼びますか?
a) 合駒 b) 入玉 c) 詰み d) 千日手
正解:c) 詰み
説明:詰みとは、相手の玉を逃げ場のない状態に追い込み、確実に勝ちを決める状態を指します。将棋の最終目標であり、詰みを狙うために様々な戦法や手筋が用いられます。
5. 穴埋め式4択
問題13:対局者が意図的に同じ手を繰り返して時間を稼ぐ行為を( )という。
a) 待った b) 長考 c) 手待ち d) ポカ
正解:c) 手待ち
説明:手待ちとは、局面を進展させずに意図的に同じ手を繰り返すことで、時間を稼いだり、相手の手を待つ戦術を指します。プロの対局では、慎重な局面で使われることがあります。
問題14:自分の駒が2つ以上の相手の駒の利きに同時にかかる状態を( )という。
a) 両取り b) 合駒 c) 捨て駒 d) 飾り駒
正解:a) 両取り
説明:両取りとは、自分の駒が相手の2つ以上の駒を同時に取れる状態を指します。相手はどちらか一方しか守れないため、有利な局面を作り出すことができます。
問題15:対局中に一度指した手を元に戻す行為を( )という。
a) 封じ手 b) 待った c) 振り駒 d) 感想戦
正解:b) 待った
説明:待ったとは、一度指した手を元に戻す行為を指します。公式な対局では認められませんが、初心者同士の練習対局などでは許される場合もあります。
6. 選択式4択
問題16:次のうち、将棋で「急戦」とは何を指しますか?
a) 長期間にわたる戦い b) 序盤から積極的に攻める戦法 c) 玉を堅固に囲う戦法 d) 同じ手を繰り返す戦術
正解:b) 序盤から積極的に攻める戦法
説明:急戦とは、序盤から積極的に攻めを仕掛ける戦法を指します。持久戦とは対照的で、スピーディーな展開が特徴です。例として、急戦矢倉や急戦四間飛車などがあります。
問題17:次のうち、将棋で「持久戦」とは何を指しますか?
a) 序盤から積極的に攻める戦法 b) 玉を堅固に囲い、長期戦を覚悟する戦法 c) 同じ手を繰り返す戦術 d) 玉を敵陣に入れる戦術
正解:b) 玉を堅固に囲い、長期戦を覚悟する戦法
説明:持久戦とは、玉を堅固に囲い、長期戦を覚悟して戦う戦法を指します。穴熊戦法や矢倉戦法など、守りを重視する戦型が該当します。
問題18:次のうち、将棋で「定石」とは何を指しますか?
a) 対局者が意図的に同じ手を繰り返すこと b) ある局面での最善とされる手順 c) 玉を敵陣に入れること d) 対局後に棋譜を振り返ること
正解:b) ある局面での最善とされる手順
説明:定石とは、ある局面において最善とされる手順や戦法を指します。将棋の序盤では、定石を覚えることで効率的に有利な局面を作り出すことができます。
7. 穴埋め式4択
問題19:対局中に、相手の意表を突くような戦法を( )という。
a) 奇襲戦法 b) 持久戦 c) 急戦 d) 合駒
正解:a) 奇襲戦法
説明:奇襲戦法とは、相手の意表を突くような戦法を指します。定石から外れた手や、予測しにくい攻めを用いることで、相手を混乱させる狙いがあります。例として、早石田や中飛車などがあります。
問題20:対局者が自分の手番を保留し、次の手を封筒に入れて提出する行為を( )という。
a) 感想戦 b) 封じ手 c) 振り駒 d) 待った
正解:b) 封じ手
説明:封じ手とは、長時間の対局において、対局が中断される際に次の手を封筒に入れて提出する行為を指します。これにより、対局の公平性が保たれ、翌日の再開時に同じ局面から対局が続けられます。
8. 穴埋め式4択
問題21:対局中に、自分の玉を詰まないようにするために、相手の攻めを防ぐ駒を打つことを( )という。
a) 合駒 b) 捨て駒 c) 浮き駒 d) 飾り駒
正解:a) 合駒
説明:合駒とは、相手の走り駒や攻めの利きを遮るために、自分の駒を打ったり動かしたりして玉を守る技術です。実戦で非常に重要な守りの手段であり、詰将棋でもよく見られる手筋です。
問題22:自分の駒が相手の駒に取られやすい位置にある状態を( )という。
a) 浮き駒 b) 合駒 c) 捨て駒 d) 両取り
正解:a) 浮き駒
説明:浮き駒とは、自分の駒が他の駒に守られず、相手に簡単に取られやすい状態にあることを指します。浮き駒は攻められやすいため、注意が必要です。
問題23:対局中に、自分の駒をあえて取らせることで、相手の陣形を崩す戦術を( )という。
a) 合駒 b) 捨て駒 c) 浮き駒 d) 飾り駒
正解:b) 捨て駒
説明:捨て駒とは、自分の駒を相手に取らせることで、相手の陣形を崩したり、次の攻めにつなげたりする戦術です。詰将棋や実戦でよく用いられる高度な技術です。
問題24:対局中に、自分の駒を動かさず、相手の手を待つ戦術を( )という。
a) 手待ち b) 長考 c) 待った d) 封じ手
正解:a) 手待ち
説明:手待ちとは、局面を進展させずに、自分の駒を動かさず、相手の手を待つ戦術を指します。慎重な局面で有効な手段であり、持久戦でよく使われます。
問題25:対局中に、自分の駒を動かして、相手の駒を同時に2つ以上取れる状態を作ることを( )という。
a) 両取り b) 合駒 c) 捨て駒 d) 浮き駒
正解:a) 両取り
説明:両取りとは、自分の駒が相手の2つ以上の駒を同時に取れる状態を作ることを指します。相手はどちらか一方しか守れないため、有利な局面を作り出すことができます。
9. 選択式4択
問題26:次のうち、将棋で「振り飛車」とは何を指しますか?
a) 玉を堅固に囲う戦法 b) 飛車を右側に振る戦法 c) 序盤から積極的に攻める戦法 d) 同じ手を繰り返す戦術
正解:b) 飛車を右側に振る戦法
説明:振り飛車とは、飛車を初期位置(2筋)から右側(3筋、4筋、5筋など)に振る戦法を指します。対して、飛車を初期位置に留める戦法は「居飛車」と呼ばれます。振り飛車は攻めと守りのバランスが特徴です。
問題27:次のうち、将棋で「居飛車」とは何を指しますか?
a) 飛車を右側に振る戦法 b) 飛車を初期位置に留める戦法 c) 玉を敵陣に入れる戦術 d) 序盤から積極的に攻める戦法
正解:b) 飛車を初期位置に留める戦法
説明:居飛車とは、飛車を初期位置(2筋)に留める戦法を指します。居飛車は矢倉や穴熊など、堅固な囲いと組み合わせることが多く、プロの対局でよく見られます。
問題28:次のうち、将棋で「穴熊」とは何を指しますか?
a) 玉を端に寄せ、堅固に囲う戦法 b) 飛車を右側に振る戦法 c) 序盤から積極的に攻める戦法 d) 同じ手を繰り返す戦術
正解:a) 玉を端に寄せ、堅固に囲う戦法
説明:穴熊とは、玉を端(1筋または9筋)に寄せ、金銀で堅固に囲う戦法を指します。守りが非常に強い反面、準備に時間がかかるため、持久戦になりやすい戦型です。
問題29:次のうち、将棋で「矢倉」とは何を指しますか?
a) 玉を中央に囲う戦法 b) 玉を端に寄せ、堅固に囲う戦法 c) 飛車を右側に振る戦法 d) 序盤から積極的に攻める戦法
正解:a) 玉を中央に囲う戦法
説明:矢倉とは、玉を中央(4~6筋)に囲い、金銀で堅固に守る戦法を指します。居飛車戦法の代表的な囲いであり、攻守のバランスが良いことが特徴です。
問題30:次のうち、将棋で「四間飛車」とは何を指しますか?
a) 飛車を3筋に振る戦法 b) 飛車を4筋に振る戦法 c) 飛車を5筋に振る戦法 d) 飛車を初期位置に留める戦法
正解:b) 飛車を4筋に振る戦法
説明:四間飛車とは、飛車を4筋に振る振り飛車戦法の一種です。四間飛車は振り飛車の基本形であり、初心者から上級者まで広く使われる戦法です。
10. 穴埋め式4択
問題31:対局中に、自分の玉を堅固に囲い、長期戦を覚悟する戦法を( )という。
a) 急戦 b) 持久戦 c) 奇襲戦法 d) 手待ち
正解:b) 持久戦
説明:持久戦とは、玉を堅固に囲い、長期戦を覚悟して戦う戦法を指します。穴熊戦法や矢倉戦法などが該当し、守りを重視する戦型です。
問題32:対局中に、序盤から積極的に攻めを仕掛ける戦法を( )という。
a) 急戦 b) 持久戦 c) 奇襲戦法 d) 手待ち
正解:a) 急戦
説明:急戦とは、序盤から積極的に攻めを仕掛ける戦法を指します。持久戦とは対照的で、スピーディーな展開が特徴です。例として、急戦矢倉や急戦四間飛車などがあります。
問題33:対局中に、相手の意表を突くような戦法を( )という。
a) 急戦 b) 持久戦 c) 奇襲戦法 d) 手待ち
正解:c) 奇襲戦法
説明:奇襲戦法とは、相手の意表を突くような戦法を指します。定石から外れた手や、予測しにくい攻めを用いることで、相手を混乱させる狙いがあります。例として、早石田や中飛車などがあります。
問題34:対局中に、ある局面での最善とされる手順を( )という。
a) 定石 b) 奇襲戦法 c) 急戦 d) 持久戦
正解:a) 定石
説明:定石とは、ある局面において最善とされる手順や戦法を指します。将棋の序盤では、定石を覚えることで効率的に有利な局面を作り出すことができます。
問題35:対局中に、自分の駒を動かさず、相手の手を待つ戦術を( )という。
a) 手待ち b) 長考 c) 待った d) 封じ手
正解:a) 手待ち
説明:手待ちとは、局面を進展させずに、自分の駒を動かさず、相手の手を待つ戦術を指します。慎重な局面で有効な手段であり、持久戦でよく使われます。
11. 選択式4択
問題36:次のうち、将棋で「中飛車」とは何を指しますか?
a) 飛車を3筋に振る戦法 b) 飛車を4筋に振る戦法 c) 飛車を5筋に振る戦法 d) 飛車を初期位置に留める戦法
正解:c) 飛車を5筋に振る戦法
説明:中飛車とは、飛車を5筋に振る振り飛車戦法の一種です。中飛車は中央を制圧する力があり、攻守のバランスが良い戦法として知られています。
問題37:次のうち、将棋で「三間飛車」とは何を指しますか?
a) 飛車を3筋に振る戦法 b) 飛車を4筋に振る戦法 c) 飛車を5筋に振る戦法 d) 飛車を初期位置に留める戦法
正解:a) 飛車を3筋に振る戦法
説明:三間飛車とは、飛車を3筋に振る振り飛車戦法の一種です。三間飛車は右玉や美濃囲いと組み合わせることが多く、柔軟な戦法として知られています。
問題38:次のうち、将棋で「石田流」とは何を指しますか?
a) 飛車を3筋に振る戦法 b) 飛車を4筋に振る戦法 c) 飛車を5筋に振る戦法 d) 飛車を初期位置に留める戦法
正解:a) 飛車を3筋に振る戦法
説明:石田流とは、三間飛車をベースにした戦法で、特に早石田(石田流急戦)が有名です。振り飛車党の間で人気があり、奇襲戦法としても用いられます。
問題39:次のうち、将棋で「右玉」とは何を指しますか?
a) 玉を右側に囲う戦法 b) 玉を左側に囲う戦法 c) 玉を中央に囲う戦法 d) 玉を端に寄せる戦法
正解:a) 玉を右側に囲う戦法
説明:右玉とは、玉を右側(1~3筋)に囲う戦法を指します。振り飛車戦法と組み合わせることが多く、柔軟な攻めが特徴です。
問題40:次のうち、将棋で「美濃囲い」とは何を指しますか?
a) 玉を右側に囲う戦法 b) 玉を左側に囲う戦法 c) 玉を中央に囲う戦法 d) 玉を端に寄せる戦法
正解:b) 玉を左側に囲う戦法
説明:美濃囲いとは、玉を左側(7~9筋)に囲い、金銀で堅固に守る戦法を指します。振り飛車戦法の代表的な囲いであり、守りが強いことが特徴です。
12. 穴埋め式4択
問題41:対局中に、玉を右側に囲う戦法を( )という。
a) 右玉 b) 美濃囲い c) 矢倉 d) 穴熊
正解:a) 右玉
説明:右玉とは、玉を右側(1~3筋)に囲う戦法を指します。振り飛車戦法と組み合わせることが多く、柔軟な攻めが特徴です。
問題42:対局中に、玉を左側に囲い、金銀で堅固に守る戦法を( )という。
a) 右玉 b) 美濃囲い c) 矢倉 d) 穴熊
正解:b) 美濃囲い
説明:美濃囲いとは、玉を左側(7~9筋)に囲い、金銀で堅固に守る戦法を指します。振り飛車戦法の代表的な囲いであり、守りが強いことが特徴です。
問題43:対局中に、玉を中央に囲い、金銀で堅固に守る戦法を( )という。
a) 右玉 b) 美濃囲い c) 矢倉 d) 穴熊
正解:c) 矢倉
説明:矢倉とは、玉を中央(4~6筋)に囲い、金銀で堅固に守る戦法を指します。居飛車戦法の代表的な囲いであり、攻守のバランスが良いことが特徴です。
問題44:対局中に、玉を端に寄せ、堅固に囲う戦法を( )という。
a) 右玉 b) 美濃囲い c) 矢倉 d) 穴熊
正解:d) 穴熊
説明:穴熊とは、玉を端(1筋または9筋)に寄せ、金銀で堅固に囲う戦法を指します。守りが非常に強い反面、準備に時間がかかるため、持久戦になりやすい戦型です。
問題45:対局中に、飛車を5筋に振る戦法を( )という。
a) 四間飛車 b) 三間飛車 c) 中飛車 d) 居飛車
正解:c) 中飛車
説明:中飛車とは、飛車を5筋に振る振り飛車戦法の一種です。中飛車は中央を制圧する力があり、攻守のバランスが良い戦法として知られています。
13. 選択式4択
問題46:次のうち、将棋で「早石田」とは何を指しますか?
a) 三間飛車をベースにした急戦 b) 四間飛車をベースにした急戦 c) 中飛車をベースにした急戦 d) 居飛車をベースにした急戦
正解:a) 三間飛車をベースにした急戦
説明:早石田とは、三間飛車をベースにした急戦戦法で、石田流の一種です。序盤から積極的に攻めることが特徴で、奇襲戦法としても用いられます。
問題47:次のうち、将棋で「角換わり」とは何を指しますか?
a) 序盤で角行を交換する戦法 b) 序盤で飛車を交換する戦法 c) 序盤で金銀を交換する戦法 d) 序盤で歩兵を交換する戦法
正解:a) 序盤で角行を交換する戦法
説明:角換わりとは、序盤で両対局者が角行を交換する戦法を指します。居飛車戦法の一種であり、激しい攻め合いが特徴です。
問題48:次のうち、将棋で「棒銀」とは何を指しますか?
a) 銀将を前に進めて攻める戦法 b) 金将を前に進めて攻める戦法 c) 角行を前に進めて攻める戦法 d) 飛車を前に進めて攻める戦法
正解:a) 銀将を前に進めて攻める戦法
説明:棒銀とは、銀将を前に進めて攻める戦法を指します。居飛車戦法の一種であり、初心者にも扱いやすい戦法として知られています。
問題49:次のうち、将棋で「腰掛け銀」とは何を指しますか?
a) 銀将を5筋に進めて攻める戦法 b) 銀将を4筋に進めて攻める戦法 c) 銀将を3筋に進めて攻める戦法 d) 銀将を2筋に進めて攻める戦法
正解:a) 銀将を5筋に進めて攻める戦法
説明:腰掛け銀とは、銀将を5筋に進めて攻める戦法を指します。角換わりや矢倉戦法でよく用いられ、攻守のバランスが良いことが特徴です。
問題50:次のうち、将棋で「袖飛車」とは何を指しますか?
a) 飛車を1筋に振る戦法 b) 飛車を2筋に振る戦法 c) 飛車を3筋に振る戦法 d) 飛車を4筋に振る戦法
正解:a) 飛車を1筋に振る戦法
説明:袖飛車とは、飛車を1筋に振る振り飛車戦法の一種です。奇襲戦法として用いられることが多く、相手の意表を突く狙いがあります。
14. 穴埋め式4択
問題51:対局中に、序盤で角行を交換する戦法を( )という。
a) 角換わり b) 棒銀 c) 腰掛け銀 d) 袖飛車
正解:a) 角換わり
説明:角換わりとは、序盤で両対局者が角行を交換する戦法を指します。居飛車戦法の一種であり、激しい攻め合いが特徴です。
問題52:対局中に、銀将を前に進めて攻める戦法を( )という。
a) 角換わり b) 棒銀 c) 腰掛け銀 d) 袖飛車
正解:b) 棒銀
説明:棒銀とは、銀将を前に進めて攻める戦法を指します。居飛車戦法の一種であり、初心者にも扱いやすい戦法として知られています。
問題53:対局中に、銀将を5筋に進めて攻める戦法を( )という。
a) 角換わり b) 棒銀 c) 腰掛け銀 d) 袖飛車
正解:c) 腰掛け銀
説明:腰掛け銀とは、銀将を5筋に進めて攻める戦法を指します。角換わりや矢倉戦法でよく用いられ、攻守のバランスが良いことが特徴です。
問題54:対局中に、飛車を1筋に振る戦法を( )という。
a) 角換わり b) 棒銀 c) 腰掛け銀 d) 袖飛車
正解:d) 袖飛車
説明:袖飛車とは、飛車を1筋に振る振り飛車戦法の一種です。奇襲戦法として用いられることが多く、相手の意表を突く狙いがあります。
問題55:対局中に、三間飛車をベースにした急戦を( )という。
a) 早石田 b) 角換わり c) 棒銀 d) 腰掛け銀
正解:a) 早石田
説明:早石田とは、三間飛車をベースにした急戦戦法で、石田流の一種です。序盤から積極的に攻めることが特徴で、奇襲戦法としても用いられます。
15. 選択式4択
問題56:次のうち、将棋で「玉の早逃げ八手詰め」という格言の意味は何ですか?
a) 玉を早く逃がすと八手で詰む b) 玉を早く逃がすと八手で勝てる c) 玉を早く囲うと八手で詰む d) 玉を早く囲うと八手で勝てる
正解:a) 玉を早く逃がすと八手で詰む
説明:「玉の早逃げ八手詰め」とは、玉を早く逃がすと、かえって簡単に詰まされてしまうことを意味する格言です。適切なタイミングで玉を動かすことが重要です。
問題57:次のうち、将棋で「飛車不成はありえない」という格言の意味は何ですか?
a) 飛車は必ず成るべきである b) 飛車は必ず成らないべきである c) 飛車は必ず交換すべきである d) 飛車は必ず動かすべきである
正解:a) 飛車は必ず成るべきである
説明:「飛車不成はありえない」とは、飛車が敵陣に入った場合、成ることで価値が高まるため、成らない選択はほぼありえないことを意味する格言です。ただし、例外もあります。
問題58:次のうち、将棋で「角の頭は歩で守れ」という格言の意味は何ですか?
a) 角行の頭に歩を打つことで守る b) 角行の頭に金銀を打つことで守る c) 角行の頭に飛車を打つことで守る d) 角行の頭に玉を動かすことで守る
正解:a) 角行の頭に歩を打つことで守る
説明:「角の頭は歩で守れ」とは、角行の頭(角が利いている筋の1つ先)に歩を打つことで、角行を守ることを意味する格言です。角行の弱点を補う基本的な手筋です。
問題59:次のうち、将棋で「金を動かすな」という格言の意味は何ですか?
a) 金将は守りに使うべきである b) 金将は攻めに使うべきである c) 金将は交換すべきである d) 金将は成るべきである
正解:a) 金将は守りに使うべきである
説明:「金を動かすな」とは、金将は玉の守りに使う駒であり、むやみに動かしてはいけないことを意味する格言です。金将は守りの要として重要な役割を果たします。
問題60:次のうち、将棋で「端歩は突くな」という格言の意味は何ですか?
a) 端歩を突くと不利になる b) 端歩を突くと有利になる c) 端歩を突くと詰みになる d) 端歩を突くと千日手になる
正解:a) 端歩を突くと不利になる
説明:「端歩は突くな」とは、むやみに端歩(1筋または9筋の歩)を突くと、相手に攻めの糸口を与えてしまい、不利になることを意味する格言です。ただし、局面によっては有効な場合もあります。
16. 穴埋め式4択
問題61:対局中に、玉を早く逃がすと簡単に詰まされてしまうことを意味する格言を( )という。
a) 玉の早逃げ八手詰め b) 飛車不成はありえない c) 角の頭は歩で守れ d) 金を動かすな
正解:a) 玉の早逃げ八手詰め
説明:「玉の早逃げ八手詰め」とは、玉を早く逃がすと、かえって簡単に詰まされてしまうことを意味する格言です。適切なタイミングで玉を動かすことが重要です。
問題62:対局中に、飛車が敵陣に入った場合、成ることで価値が高まるため、成らない選択はほぼありえないことを意味する格言を( )という。
a) 玉の早逃げ八手詰め b) 飛車不成はありえない c) 角の頭は歩で守れ d) 金を動かすな
正解:b) 飛車不成はありえない
説明:「飛車不成はありえない」とは、飛車が敵陣に入った場合、成ることで価値が高まるため、成らない選択はほぼありえないことを意味する格言です。ただし、例外もあります。
問題63:対局中に、角行の頭に歩を打つことで、角行を守ることを意味する格言を( )という。
a) 玉の早逃げ八手詰め b) 飛車不成はありえない c) 角の頭は歩で守れ d) 金を動かすな
正解:c) 角の頭は歩で守れ
説明:「角の頭は歩で守れ」とは、角行の頭(角が利いている筋の1つ先)に歩を打つことで、角行を守ることを意味する格言です。角行の弱点を補う基本的な手筋です。
問題64:対局中に、金将は玉の守りに使う駒であり、むやみに動かしてはいけないことを意味する格言を( )という。
a) 玉の早逃げ八手詰め b) 飛車不成はありえない c) 角の頭は歩で守れ d) 金を動かすな
正解:d) 金を動かすな
説明:「金を動かすな」とは、金将は玉の守りに使う駒であり、むやみに動かしてはいけないことを意味する格言です。金将は守りの要として重要な役割を果たします。
問題65:対局中に、むやみに端歩を突くと、相手に攻めの糸口を与えてしまい、不利になることを意味する格言を( )という。
a) 端歩は突くな b) 玉の早逃げ八手詰め c) 飛車不成はありえない d) 角の頭は歩で守れ
正解:a) 端歩は突くな
説明:「端歩は突くな」とは、むやみに端歩(1筋または9筋の歩)を突くと、相手に攻めの糸口を与えてしまい、不利になることを意味する格言です。ただし、局面によっては有効な場合もあります。
17. 選択式4択
問題66:次のうち、将棋で「詰将棋」とは何を指しますか?
a) 実際の対局で詰みを狙うこと b) 特定の局面から玉を詰ませる問題を解くこと c) 対局後に棋譜を振り返ること d) 対局中に同じ手を繰り返すこと
正解:b) 特定の局面から玉を詰ませる問題を解くこと
説明:詰将棋とは、特定の局面から相手の玉を確実に詰ませる手順を考える問題を指します。詰将棋を解くことで、終盤力や手筋の理解が深まります。
問題67:次のうち、将棋で「必至」とは何を指しますか?
a) 相手の玉を確実に詰ませる状態 b) 相手の駒を確実に取れる状態 c) 自分の玉を確実に守れる状態 d) 相手の玉を確実に詰ませられない状態
正解:a) 相手の玉を確実に詰ませる状態
説明:必至とは、相手の玉を確実に詰ませる状態を指します。詰将棋の一種であり、相手がどのような手を指しても詰みを逃れられない状態です。
問題68:次のうち、将棋で「とどめ」とは何を指しますか?
a) 相手の玉を逃げられないようにする最終的な一手 b) 相手の駒を取る手 c) 自分の玉を守る手 d) 相手の駒を交換する手
正解:a) 相手の玉を逃げられないようにする最終的な一手
説明:とどめとは、詰将棋や実戦で、相手の玉を逃げられないようにする最終的な一手を指します。詰みを完成させるための重要な手です。
問題69:次のうち、将棋で「詰めろ」とは何を指しますか?
a) 相手の玉を次の一手で詰ませられる状態 b) 相手の駒を次の一手で取れる状態 c) 自分の玉を次の一手で守れる状態 d) 相手の玉を次の一手で詰ませられない状態
正解:a) 相手の玉を次の一手で詰ませられる状態
説明:詰めろとは、相手の玉を次の一手で詰ませられる状態を指します。相手が適切な手を指さない限り、詰みが確定する状態です。
問題70:次のうち、将棋で「王手」とは何を指しますか?
a) 相手の玉を直接攻撃する手 b) 相手の駒を取る手 c) 自分の玉を守る手 d) 相手の駒を交換する手
正解:a) 相手の玉を直接攻撃する手
説明:王手とは、相手の玉を直接攻撃する手を指します。王手をかけられた側は、必ず王手を解除する手を指さなければなりません。
18. 穴埋め式4択
問題71:対局中に、特定の局面から相手の玉を確実に詰ませる手順を考える問題を( )という。
a) 詰将棋 b) 必至 c) とどめ d) 詰めろ
正解:a) 詰将棋
説明:詰将棋とは、特定の局面から相手の玉を確実に詰ませる手順を考える問題を指します。詰将棋を解くことで、終盤力や手筋の理解が深まります。
問題72:対局中に、相手の玉を確実に詰ませる状態を( )という。
a) 詰将棋 b) 必至 c) とどめ d) 詰めろ
正解:b) 必至
説明:必至とは、相手の玉を確実に詰ませる状態を指します。詰将棋の一種であり、相手がどのような手を指しても詰みを逃れられない状態です。
問題73:対局中に、相手の玉を逃げられないようにする最終的な一手を( )という。
a) 詰将棋 b) 必至 c) とどめ d) 詰めろ
正解:c) とどめ
説明:とどめとは、詰将棋や実戦で、相手の玉を逃げられないようにする最終的な一手を指します。詰みを完成させるための重要な手です。
問題74:対局中に、相手の玉を次の一手で詰ませられる状態を( )という。
a) 詰将棋 b) 必至 c) とどめ d) 詰めろ
正解:d) 詰めろ
説明:詰めろとは、相手の玉を次の一手で詰ませられる状態を指します。相手が適切な手を指さない限り、詰みが確定する状態です。
問題75:対局中に、相手の玉を直接攻撃する手を( )という。
a) 王手 b) 詰将棋 c) 必至 d) とどめ
正解:a) 王手
説明:王手とは、相手の玉を直接攻撃する手を指します。王手をかけられた側は、必ず王手を解除する手を指さなければなりません。
19. 選択式4択
問題76:次のうち、将棋で「持将棋」とは何を指しますか?
a) 双方が入玉し、勝敗が決まらない状態 b) 双方が同じ手を繰り返す状態 c) 相手の玉を確実に詰ませる状態 d) 自分の玉を確実に守れる状態
正解:a) 双方が入玉し、勝敗が決まらない状態
説明:持将棋とは、双方が入玉し、どちらも詰まない状態が続き、勝敗が決まらない状態を指します。この場合、引き分けとなります。
問題77:次のうち、将棋で「千日手」とは何を指しますか?
a) 双方が入玉し、勝敗が決まらない状態 b) 双方が同じ手を繰り返す状態 c) 相手の玉を確実に詰ませる状態 d) 自分の玉を確実に守れる状態
正解:b) 双方が同じ手を繰り返す状態
説明:千日手とは、両対局者が同じ手順を繰り返し、局面が全く進展しない状態を指します。ルール上、4回同じ局面が繰り返されると引き分けとなります。
問題78:次のうち、将棋で「封じ手」とは何を指しますか?
a) 対局中に次の手を封筒に入れて提出すること b) 対局後に棋譜を振り返ること c) 対局中に同じ手を繰り返すこと d) 対局中に一度指した手を元に戻すこと
正解:a) 対局中に次の手を封筒に入れて提出すること
説明:封じ手とは、長時間の対局において、対局が中断される際に次の手を封筒に入れて提出する行為を指します。これにより、対局の公平性が保たれ、翌日の再開時に同じ局面から対局が続けられます。
問題79:次のうち、将棋で「感想戦」とは何を指しますか?
a) 対局中に次の手を封筒に入れて提出すること b) 対局後に棋譜を振り返ること c) 対局中に同じ手を繰り返すこと d) 対局中に一度指した手を元に戻すこと
正解:b) 対局後に棋譜を振り返ること
説明:感想戦とは、対局終了後に両対局者が棋譜を見ながら、試合の進行や手順について振り返り、意見を交換することを指します。プロの対局では、感想戦を通じて学びや反省が行われます。
問題80:次のうち、将棋で「振り駒」とは何を指しますか?
a) 対局前に先手後手を決めるために歩を振ること b) 対局中に次の手を封筒に入れて提出すること c) 対局後に棋譜を振り返ること d) 対局中に同じ手を繰り返すこと
正解:a) 対局前に先手後手を決めるために歩を振ること
説明:振り駒とは、対局前に先手後手を決めるために、歩兵の駒を振ることを指します。歩の表が出れば先手、裏が出れば後手となります。
20. 穴埋め式4択
問題81:対局中に、双方が入玉し、勝敗が決まらない状態を( )という。
a) 持将棋 b) 千日手 c) 封じ手 d) 感想戦
正解:a) 持将棋
説明:持将棋とは、双方が入玉し、どちらも詰まない状態が続き、勝敗が決まらない状態を指します。この場合、引き分けとなります。
問題82:対局中に、双方が同じ手を繰り返す状態を( )という。
a) 持将棋 b) 千日手 c) 封じ手 d) 感想戦
正解:b) 千日手
説明:千日手とは、両対局者が同じ手順を繰り返し、局面が全く進展しない状態を指します。ルール上、4回同じ局面が繰り返されると引き分けとなります。
問題83:対局中に、次の手を封筒に入れて提出することを( )という。
a) 持将棋 b) 千日手 c) 封じ手 d) 感想戦
正解:c) 封じ手
説明:封じ手とは、長時間の対局において、対局が中断される際に次の手を封筒に入れて提出する行為を指します。これにより、対局の公平性が保たれ、翌日の再開時に同じ局面から対局が続けられます。
問題84:対局後に、棋譜を振り返ることを( )という。
a) 持将棋 b) 千日手 c) 封じ手 d) 感想戦
正解:d) 感想戦
説明:感想戦とは、対局終了後に両対局者が棋譜を見ながら、試合の進行や手順について振り返り、意見を交換することを指します。プロの対局では、感想戦を通じて学びや反省が行われます。
問題85:対局前に、先手後手を決めるために歩を振ることを( )という。
a) 振り駒 b) 持将棋 c) 千日手 d) 封じ手
正解:a) 振り駒
説明:振り駒とは、対局前に先手後手を決めるために、歩兵の駒を振ることを指します。歩の表が出れば先手、裏が出れば後手となります。
21. 選択式4択
問題86:次のうち、将棋のタイトル戦で最も歴史が長いものはどれですか?
a) 竜王戦 b) 名人戦 c) 王位戦 d) 王座戦
正解:b) 名人戦
説明:名人戦は将棋のタイトル戦の中で最も歴史が長く、1935年に開始されました。名人位は将棋界の最高位とされ、プロ棋士の憧れのタイトルです。
問題87:次のうち、将棋のタイトル戦で最も賞金が高いものはどれですか?
a) 竜王戦 b) 名人戦 c) 王位戦 d) 王座戦
正解:a) 竜王戦
説明:竜王戦は将棋のタイトル戦の中で最も賞金が高く、優勝賞金は約4400万円(2025年現在)です。竜王位は名人と並ぶ最高位のタイトルとされています。
問題88:次のうち、将棋のタイトル戦で「永世称号」が得られるものはどれですか?
a) 竜王戦 b) 名人戦 c) 王位戦 d) すべてのタイトル戦
正解:d) すべてのタイトル戦
説明:将棋のタイトル戦では、一定の条件を満たすことで「永世称号」が得られます。たとえば、名人で5期連続または通算10期獲得すると「永世名人」となります。
問題89:次のうち、将棋のタイトル戦で「七冠」を達成した棋士は誰ですか?
a) 羽生善治 b) 藤井聡太 c) 中原誠 d) 大山康晴
正解:a) 羽生善治
説明:羽生善治は1996年に将棋のタイトル戦で「七冠」を達成しました。これは将棋史上初の快挙であり、羽生の強さを象徴する記録です。
問題90:次のうち、将棋のタイトル戦で「八冠」を達成した棋士は誰ですか?
a) 羽生善治 b) 藤井聡太 c) 中原誠 d) 大山康晴
正解:b) 藤井聡太
説明:藤井聡太は2023年に将棋のタイトル戦で「八冠」を達成しました。これは将棋史上初の快挙であり、藤井の圧倒的な強さを示す記録です。
22. 穴埋め式4択
問題91:将棋のタイトル戦で、最も歴史が長いものは( )です。
a) 竜王戦 b) 名人戦 c) 王位戦 d) 王座戦
正解:b) 名人戦
説明:名人戦は将棋のタイトル戦の中で最も歴史が長く、1935年に開始されました。名人位は将棋界の最高位とされ、プロ棋士の憧れのタイトルです。
問題92:将棋のタイトル戦で、最も賞金が高いものは( )です。
a) 竜王戦 b) 名人戦 c) 王位戦 d) 王座戦
正解:a) 竜王戦
説明:竜王戦は将棋のタイトル戦の中で最も賞金が高く、優勝賞金は約4400万円(2025年現在)です。竜王位は名人と並ぶ最高位のタイトルとされています。
問題93:将棋のタイトル戦で、一定の条件を満たすことで得られる称号を( )という。
a) 永世称号 b) 名人位 c) 竜王位 d) 七冠
正解:a) 永世称号
説明:将棋のタイトル戦では、一定の条件を満たすことで「永世称号」が得られます。たとえば、名人で5期連続または通算10期獲得すると「永世名人」となります。
問題94:将棋のタイトル戦で、「七冠」を達成した棋士は( )です。
a) 羽生善治 b) 藤井聡太 c) 中原誠 d) 大山康晴
正解:a) 羽生善治
説明:羽生善治は1996年に将棋のタイトル戦で「七冠」を達成しました。これは将棋史上初の快挙であり、羽生の強さを象徴する記録です。
問題95:将棋のタイトル戦で、「八冠」を達成した棋士は( )です。
a) 羽生善治 b) 藤井聡太 c) 中原誠 d) 大山康晴
正解:b) 藤井聡太
説明:藤井聡太は2023年に将棋のタイトル戦で「八冠」を達成しました。これは将棋史上初の快挙であり、藤井の圧倒的な強さを示す記録です。
23. 選択式4択
問題96:次のうち、将棋の駒で「成駒」にならないものはどれですか?
a) 歩兵 b) 桂馬 c) 金将 d) 銀将
正解:c) 金将
説明:将棋の駒のうち、金将と玉将は成ることができません。歩兵、桂馬、銀将、香車、飛車、角行は敵陣に入るか、敵陣で動くことで成駒になります。
問題97:次のうち、将棋の駒で最も価値が高いものはどれですか?
a) 飛車 b) 角行 c) 金将 d) 銀将
正解:a) 飛車
説明:将棋の駒の価値は、飛車が最も高く、次に角行、金将、銀将の順になります。飛車は遠距離の利きを持つ大駒であり、攻守の要として重要です。
問題98:次のうち、将棋の駒で最も動きが少ないものはどれですか?
a) 歩兵 b) 桂馬 c) 銀将 d) 香車
正解:a) 歩兵
説明:将棋の駒のうち、歩兵は1マス前に進むことしかできないため、最も動きが少ない駒です。ただし、成ると「と金」になり、動きが増えます。
問題99:次のうち、将棋の駒で最も遠くまで動けるものはどれですか?
a) 飛車 b) 角行 c) 香車 d) 桂馬
正解:a) 飛車
説明:将棋の駒のうち、飛車は縦横に何マスでも動けるため、最も遠くまで動ける駒です。飛車は「走り駒」としても知られ、攻守の要として重要です。
問題100:次のうち、将棋の駒で「大駒」と呼ばれるものはどれですか?
a) 歩兵 b) 桂馬 c) 飛車 d) 銀将
正解:c) 飛車
説明:大駒とは、将棋において価値が高く、遠距離の利きを持つ駒のことで、具体的には飛車と角行を指します。対して、歩兵、桂馬、銀将などは「小駒」と呼ばれます。
24. 穴埋め式4択
問題101:将棋の駒のうち、成ることができないものは( )です。
a) 歩兵 b) 桂馬 c) 金将 d) 銀将
正解:c) 金将
説明:将棋の駒のうち、金将と玉将は成ることができません。歩兵、桂馬、銀将、香車、飛車、角行は敵陣に入るか、敵陣で動くことで成駒になります。
問題102:将棋の駒のうち、最も価値が高いものは( )です。
a) 飛車 b) 角行 c) 金将 d) 銀将
正解:a) 飛車
説明:将棋の駒の価値は、飛車が最も高く、次に角行、金将、銀将の順になります。飛車は遠距離の利きを持つ大駒であり、攻守の要として重要です。
問題103:将棋の駒のうち、最も動きが少ないものは( )です。
a) 歩兵 b) 桂馬 c) 銀将 d) 香車
正解:a) 歩兵
説明:将棋の駒のうち、歩兵は1マス前に進むことしかできないため、最も動きが少ない駒です。ただし、成ると「と金」になり、動きが増えます。
問題104:将棋の駒のうち、最も遠くまで動けるものは( )です。
a) 飛車 b) 角行 c) 香車 d) 桂馬
正解:a) 飛車
説明:将棋の駒のうち、飛車は縦横に何マスでも動けるため、最も遠くまで動ける駒です。飛車は「走り駒」としても知られ、攻守の要として重要です。
問題105:将棋の駒のうち、「大駒」と呼ばれるものは( )です。
a) 歩兵 b) 桂馬 c) 飛車 d) 銀将
正解:c) 飛車
説明:大駒とは、将棋において価値が高く、遠距離の利きを持つ駒のことで、具体的には飛車と角行を指します。対して、歩兵、桂馬、銀将などは「小駒」と呼ばれます。
25. 選択式4択(追加問題)
問題106:次のうち、将棋のルールで「二歩」とは何を指しますか?
a) 同じ筋に2つの歩を打つこと b) 同じ筋に2つの金を打つこと c) 同じ筋に2つの銀を打つこと d) 同じ筋に2つの飛車を打つこと
正解:a) 同じ筋に2つの歩を打つこと
説明:二歩とは、同じ筋に2つの歩を打つことを指し、将棋のルールで禁止されています。これは、歩の特性上、進行を妨げるためです。
問題107:次のうち、将棋のルールで「打ち歩詰め」とは何を指しますか?
a) 歩を打って相手の玉を詰ませること b) 歩を打って自分の玉を詰ませること c) 歩を打って相手の駒を取ること d) 歩を打って自分の駒を守ること
正解:a) 歩を打って相手の玉を詰ませること
説明:打ち歩詰めとは、歩を打つことで相手の玉を詰ませることを指します。ただし、将棋のルールでは、打ち歩詰めは禁止されており、負けとなります。
問題108:次のうち、将棋のルールで「連続王手の千日手」とは何を指しますか?
a) 連続で王手をかけ、同じ局面が繰り返されること b) 連続で駒を取り、同じ局面が繰り返されること c) 連続で玉を動かし、同じ局面が繰り返されること d) 連続で歩を突き、同じ局面が繰り返されること
正解:a) 連続で王手をかけ、同じ局面が繰り返されること
説明:連続王手の千日手とは、連続で王手をかけ、同じ局面が4回繰り返される状態を指します。この場合、王手をかけた側が負けとなります。
問題109:次のうち、将棋のルールで「持駒」とは何を指しますか?
a) 盤上にある自分の駒 b) 盤上にある相手の駒 c) 取った相手の駒 d) 取られた自分の駒
正解:c) 取った相手の駒
説明:持駒とは、対局中に取った相手の駒を指します。持駒は自分の手番に盤上に打つことができ、攻守の戦略に大きな影響を与えます。
問題110:次のうち、将棋のルールで「成駒」とは何を指しますか?
a) 敵陣に入った駒が変化したもの b) 盤上にある自分の駒 c) 盤上にある相手の駒 d) 取った相手の駒
正解:a) 敵陣に入った駒が変化したもの
説明:成駒とは、歩兵、桂馬、銀将、香車、飛車、角行が敵陣(相手の3段目以内)に入るか、敵陣で動くことで変化した駒を指します。成駒は動きが増え、強力になります。






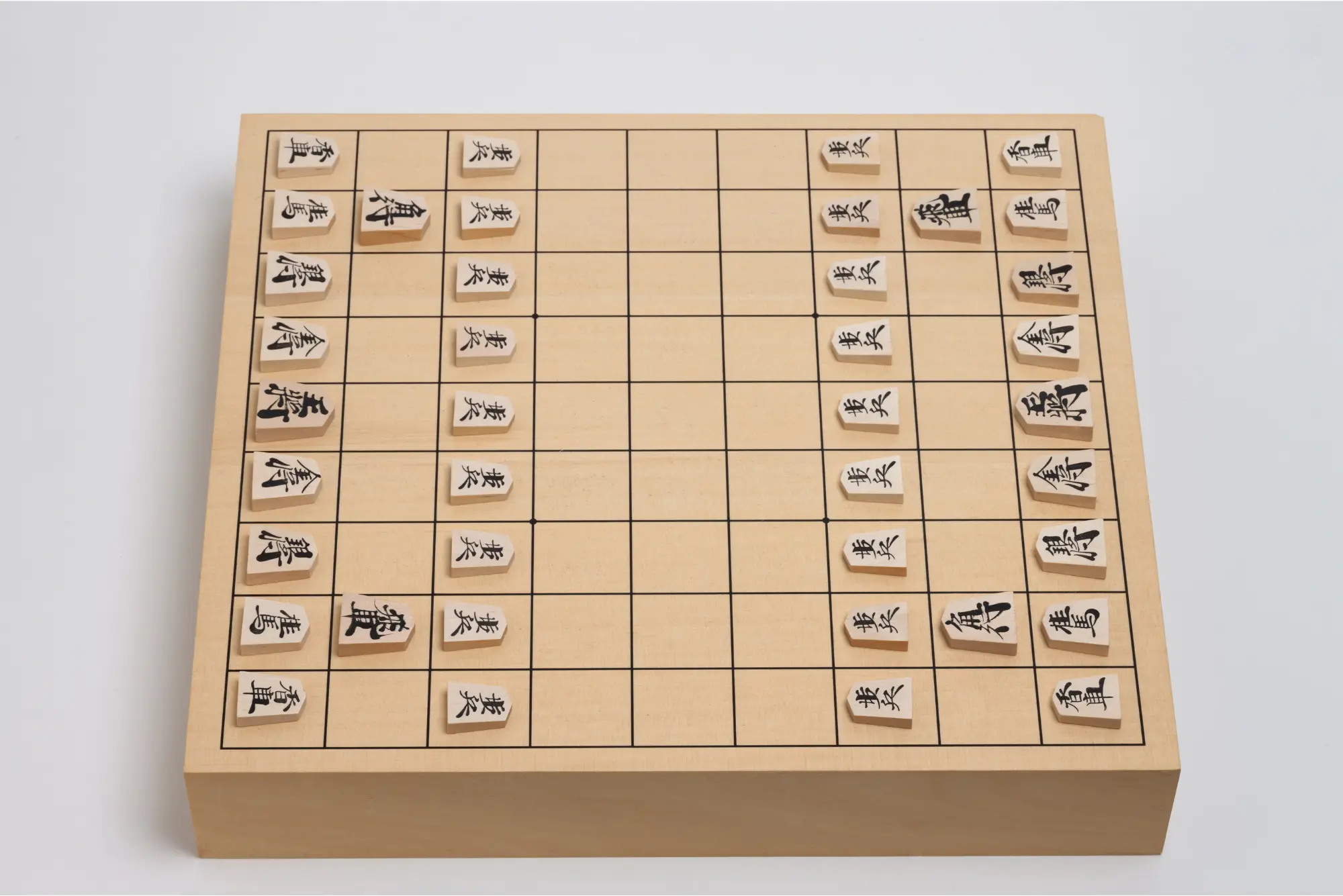


コメント